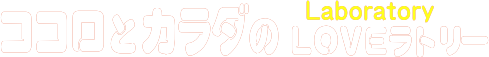肩こり、腰痛、背中の痛みの原因には・・・
- 単純な背中の筋肉疲労によるもの
- 背中や背骨のケガ
- 日常生活における姿勢からくるゆがみ
- 胃、肺、肝臓などの内臓の反射による痛みなど
実に様々なものがあります。
背中まわりの筋肉や骨などの組織に直接的なケガがなくても、<こり>や<痛み>を感じることがあります。内臓の疲れや病気が<こり>や<痛み>の原因となっている可能性があります。
そんなカラダの中で起こっていることを内臓調整療法師として、ご説明していきます。
内臓体壁反射(ないぞうたいへきはんしゃ)とは?
受容器→求心性神経→反射中枢→遠心性神経→効果器(応じる器官)
感覚受容器(筋肉や内臓)からの刺激や興奮が、神経線維を通して脊髄や延髄、脳などの中枢神経(ちゅうすうしんけい)に情報が伝えられ、中枢から各部位・応じる器官に一定の反応を示す。一定の反応は、体壁(たいへき)に様々な形となって現れる。反射による体壁(たいへき)を読み解くことで、コリや痛み、そして体の歪みの主な原因を追及していくことが大切になってきます。
体壁(たいへき)とは、胴体(=体幹)の内臓を守るように取り囲んでいる筋肉と一部骨でできた壁のこと。 胸部の胸壁、腹部の腹壁に分けられる。引用:一年生の解剖学辞典
内臓がオーバーワーク気味になったり、機能低下していると自律神経が乱れる。自律神経が乱れると内蔵がオーバーワーク気味になったり、機能が低下する。その乱れが見えるような形で体表(たいひょう)に現れてくるのです。食べ過ぎは、肩こりの原因になるってご存知ですか?
- 首が斜めに傾く。
- 背骨の稼働域が狭くなる。
- 痛みが出る。
- 姿勢の乱れ。
体壁に投影され、運動系・知覚系・自律系なのに渡って複雑な内容を持つ反射症候群が現れる。これを連関反射という。以下、運動系・知覚系など5種類に分類してまとめられている。
①内臓⇒体壁運動の反射

内臓からの感じた衝動が、対応する体壁の骨格筋群が縮んだり、硬くなったりする。これが要するにコリの原因と言われ、内臓疾患による筋性防御である。これらは、インパルスが伝えられた皮膚分節に対応して、分節的に表れるが、インパルスが大き過ぎるとその分節にとどまらず、別の分節にも広がって現れる。下の図は、デルマトーム:皮膚分節(皮膚知覚帯)を表現している。

出典:『ネッター』南江堂
内臓の炎症や過度の伸びや腫れ(はれ)、虚血(きょけつ)などにより、激しい腹痛が起きると無意識に腹筋を緊張させ、さらに腹部を抑えたり体を折り曲げてその痛みをこらえようとします。
筋肉が硬くなるのは一時的なものですが、慢性の病変などにより、長期化すると筋肉は変性や萎縮(いしゅく)を伴います。
腹筋や脚を曲げる筋肉が反射的に縮まる。
反射的に縮まる・・・この収縮を筋性防御(きんせいぼうぎょ)といい、虫垂炎や腹膜炎の診断に活用されています。
例えば・・・肥厚(ひこう)の出やすい場所
- 左心室(心臓)は、胸椎(Th)左2番~4番
- 右心室(心臓)は、胸椎(Th)右2番~4番
- 逆流性食道連は、胸椎(Th)5番
- 胃は、胸椎(Th)左5番~9番番
- 膵臓(すいぞう)は、胸椎(Th)左6番~11番
- 肝臓は、胸椎(Th)右6番~10番・腰椎(L)1番・・・腰の回旋(かいせん)として出やすい。
- 胆のうは、胸椎(Th)右6番~9番・腰椎(L)2番・・・腰の側屈(そっくつ)として出やすい。
②内臓⇒体壁知覚の反射

内臓からの異常な刺激により、通常なら疼痛(とうつう)とはならない箇所の皮膚に刺激を与えると過敏に反応する。疼痛や不快な感覚がある。これを関連痛(かんれんつう)といいます。
関連痛とは?
関連痛とは、以上のある内臓からの自律神経求心路と同じ脊髄分節に入る体性神経が分布する皮膚や筋肉に生じる痛み。脳はそこに関連する皮膚の痛みとして知覚される。関連痛の出現部位

出典:『人体の正常構造と機能』日本医事新報社
みぞおちのあたりを押さえて胃のあたりが痛いという場合も、実は胃そのものに痛みを感じる知覚神経はない。その反射が中枢神経を通して反射された関連する部位の皮膚が痛いと感じることで、胃のあたりが不快に感じる。脳は胃が炎症していても、胃そのものを痛いと感じるのではなく、胃のあたりの皮膚が痛いと言った方が厳密かもしれませんね。
③内臓⇒体壁栄養反射

①と②は、主に急性疾患である。それに対して③は、長期化・慢性する事によって、必要な血液が供給されず、関連する筋肉が栄養不足に陥った状態をさす。関連する神経支配下のデルマトーム、ミオトームに変性萎縮が現れる事が多い。
胃や心臓の疲れにより、背中の筋肉がやせ細ってきたりする現象。
④内臓⇒体壁自律系反射

汗腺、皮脂腺、立毛筋や末梢血管系に投影する反射。内臓の疲れなどによる反射から、急に汗をかいたり、鳥肌が立ったりするのは、内臓-体壁自律系反射といいます。
⑤内臓⇒内臓反射

とある内臓からのインパルスが、他の内臓に投影する場合。胃から結腸や大動脈や首の動脈洞、そして吐き気などは、迷走神経求心路によるものである。肝臓の疲れから心臓や腎臓にも影響がでたりすることを内臓ー内臓反射といいます。
肝心・肝腎という言葉もこの反射から生まれたのでしょう。
①から⑤以外にも、内臓調整療法師会にて講義が行われましたが、詳細については、別の投稿をご覧ください。
まとめ

今回は、難しい内容となってしまいましたが、最後まで一読して下さりありがとうございます。
- 内臓が疲れているから体が歪む。
- 姿勢を悪くしているから内臓が疲れやすくなる。
双方は複雑にからみあっています。