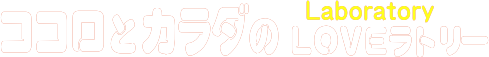「胸やけがする」「ゲップが出やすい」と悩んでいるあなたへ!
そんな症状が続いているとしたら、逆流性食道炎(ぎゃくりゅうせいしょくどうえん)なのかもしれませんよ。


- 「胸のあたりが、きりきり痛い」
- 「夜、横になると口が酸っぱくなって眠れない」
- 「ゲップが出やすく、肩こりが長引いている」
そんな悩みをかかえるあなたへ 今、急上昇中! 逆流性食道炎の原因と解消法についてまとめてみました。
背中に触れ続けてきた内臓調整療法師だからこそ伝えたいこと、お伝えいたします。
逆流性食道炎とは?

そもそも逆流性食道炎とは、胃の中に入った食べ物や胃酸が、本来戻らないはずの食道に逆流することに始まります。
胃は、強い酸性の胃酸から守るために日々修復作業を行っています。しかし、食道は胃酸の強力な酸性には耐えられない。
強い酸性が、食道に逆流することで、炎症し、胸やけや胸の痛みだけでなく、肩こりなどといった症状もあらわれます。


- 胃に食べ物が長くとどまっている:食べ過ぎ・よく噛まない・肉など消化に時間がかかるもの・食べる時間が不規則
- 噴門の機能低下:上記の食生活に加えて・・・姿勢の乱れ・肥満・加齢
食生活の乱れは、胃そのものだけではなく、胃の入り口の負担にもなってしまうことが逆流性食道炎になりやすい原因です。
食べ過ぎで、肩こりが長引く人は、肩こりがひどい原因は、食べ過ぎにあった?もご覧ください。



喉元(のどもと)すぎれば熱さ忘れる・・・
「あまりつらいと感じない」人ほど症状を悪化させてしまう原因になってしまいます。
ここで、逆流性食道炎の具体的症状をまとめてみましたので、ご覧ください。
具体的症状とは?
胸やけ・吐き気

胃のあたりがキリキリしたり、ムカムカしたりします。
この胸やけや吐き気が逆流性食道炎の人の症状として一番多いと言われいます。
これをお読みのあなたは、胸やけや吐き気で悩んでいらっしゃるかもしれませんね。ゲップが出やすい人も多いです。
呑酸(どんさん)

口の中で、異様な酸っぱさを感じる。 胃から口にまで上がってきた胃酸が酸っぱさを感じさせてしまいます。
特に夜、横になったときにこの症状で悩むかたが多いようです。
喉(のど)があれたり、咳が出る。

喉の炎症。
胃から上がってきた胃酸が原因で、喉があれてしまいます。喉のイガイガする深いな症状は、逆流性食道炎が原因かもしれませんね。
口臭の原因

昔から「息が臭うと、胃が悪いのかな?」と思っている方も多いですよね。
胃から逆流する胃酸のすっぱい臭いは、口臭の原因。もし、口臭が気になるようでしたら、胃に優しい生活をココロがけるべきです。
肩や背中・胸の痛み

内臓調整療法師会では、内臓体壁反射(ないぞうたいへきはんしゃ)により、胸椎(きょうつい):背中の5番目の骨が本来の姿勢から比べて、奥に沈んでいる人が多く見受けられます。
このことにより、
- 胸のしめつけ
- 背中の張り
- 胸やけ
- 肩こり
が長引く可能性があります。
思いあたる方は、こちらもご覧ください⇒どうして背中が張るのかな? 整体に行っても張るのかな? 背中が張る本当の原因とは?
ちなみに脊柱(せきちゅう)と呼ばれる背骨は32~34子の骨で形成されています。
- 首:頸椎(けいつい):7個(まれに8個の人も)
- 胸:胸椎(きょうつい):12個・・・逆流性食道炎は、この上から5番目
- 腰:腰椎(ようつい):5個(6個の人もいました)
- お尻:仙椎(せんつい):5個(仙骨(せんこつ)と呼ぶ方が一般的)
- お尻:尾椎(びつい):3~5個(尾骨(びこつ)と呼ぶ方が一般的)
一般的な治療方法とは?
胃酸を抑える。

治療は、出過ぎた胃酸を抑えるために、お薬が出されることが多いようです。
重症化された場合は、手術に発展することもあるので、ご用心!
残念ながら、現在使われている薬では、逆流する胃酸を根本から治すことができないため、薬を長く飲み続ける治療法が主流となっています。
そのために、薬を飲み続ける事で、再発を予防する”維持療法”が進められているのが現状です。
逆流性食道炎は、再発を繰り返す人が多い。
「もうこれは、一生付き合っていくしかないのかな?」とがっかりしていませんか?
カラダからの声を聴きながら、カラダの基本に立ち返って「どうして胃酸が逆流しているのか?」ご一緒に考えてみましょう!
逆流性食道炎を前向きに考えてみましょう。
症状は、カラダが治そうとする反応。

風邪を例に、症状とは何かを考えてみましょう。
風邪を引いたりしたとき、熱が出たり、咳がでたりしたとき、風邪の症状を必死にとめようとしていませんか?
熱や咳、くしゃみなどは、病気そのものではなく、カラダを治そうとする反応。
下手に熱を下げたり、咳やくしゃみといった「症状を抑えてしまうとカラダから毒素を出そうとする力」が邪魔されてしまいます。風邪そのものが長引いたり、こじらせてしまう原因にもなってしまうでしょう。
と・・・言うことは?

食べ過ぎや消化不良で、胃酸の逆流を防ぎきれない。しかし、逆流が起こっているのは、胃や他の内臓を守るために起こしている場合もあるんです。
胃酸が逆流するのは、もう食べ過ぎですよというカラダからの警告なのかもしれませんよ!
逆流が心臓や肺を守っている?

胃の拡張・・・胃がガスで大きくなることは、胃の負担だけではありません。
胃が拡張し、胃の上にある横隔膜が押し上げられると心臓や肺も押されてしまいます。
横隔膜による圧迫は、呼吸が困難になったり、心臓の負担から、カラダ全体に充分な血液を送り続けることを邪魔してしまうのです。
逆流が食道や気道を守っている?

胃酸という強い酸で食道や気道に付着した痰(たん)を消毒し洗い流す役割もあります。
いつまでも、食道や気道に痰を残しておくと、免疫力を低下させ、病原菌に抵抗する力が弱まってしまいます。

食道炎が食欲を抑えている?

胃や腸が弱まって、「もう消化は限界だから、これ以上食べないで!」というカラダからのメッセージでもあります。胸やけして食欲がわかないのに、胃薬を片手に「食べなくっちゃ」という「ウソの空腹感」で、食べ物を詰め込むのはやめましょう。
空腹時間を作るということは、胃や腸の修復作業時間を確保するということでもあるのです。
逆流性食道炎の対処法とは?
では、長引く逆流性食道炎には、どのように対処していけばいいのでしょうか?



大切なのは・・・
- どうして胃がたくさん胃酸を出しているか?
- どうして胃が膨張・拡張しているか?
知っておく必要があります。
胃酸が過剰に出る訳とは?
他の消化機能を補うために胃酸を出している。

胃液が過剰に出るには、意味があります。胃液は、消化酵素が含まれた消化液。
でんぷん・たんぱく質・中性脂肪・コレステロールエステルは、それぞれ分解する場所が異なります。
よく噛まず、唾液を出し切っていなかったり、胆汁や膵液が分泌(ぶんぴつ)されないと、それを補うために胃液が過剰に分泌されます。
いい唾液を出すために、「よく噛む」というのは、あなたが思っている以上に重要なのです。
しかし、胆汁や膵液を出すカラダになるためには、日ごろの生活習慣が必須。一日やそこらで出せるという訳ではないことを自覚しよう。
日頃から、重要な消化酵素である胆汁や膵液を出せない状況で、更に薬などで、胃酸を抑えてしまったらどうなると思いますか?
胃薬など、胃酸を抑える薬で、消化の最後の砦を失ってしまうかもしれないのです。最後の砦を失えば、どうやってカラダに必要な栄養素を取り込むことができなくなってしまいます。
食べても食べても、栄養不足。栄養不足で、カラダが食事を求め、食べ過ぎになるという悪循環を断ち切りましょう。
食べ過ぎや糖質・脂質のとりすぎ。

揚げ物やショートケーキなど脂っぽいものをたくさん食べると、消化がしにくいため、食べ物は長く胃にとどまることになります。長くとどめるために、胃の出口:幽門(ゆうもん)は閉じられます。
脂っぽいものや、甘いものをつい食べ過ぎて、その後、ムカムカ・・・胸やけをしたことはありませんか?
胃の中に食べたものが、長くとどまるためと胃の中の圧力が高まったり、胃が拡張したりしやすくなります。また脂質のとり過ぎにより、胆のうから十二指腸へ流れる胆管(たんかん)が詰まりやすくなってしまいます。胆汁の流れが詰まりが激しくなると胃の中に胆汁が逆流する事も胃の膨満の原因となります。糖質制限ダイエット~どうせ頑張るのなら美容と健康にも有効な6つの注意事項とは?
「もうこれ以上胃が膨らんだら、横隔膜(おうかくまく)が持ち上げられて、心臓や肺が圧迫される」と危険を感じたとき、胃の入り口:噴門を開いて、食道へと逆流させて、胃の中の圧力を抑えているのです。
胃酸過剰分泌の原因となっている唾液と胆汁と膵液の分泌不足を解消することで、胃酸を過剰に出す必要をなくすことが、逆流性食道炎の解消法となるのです。
唾液と胆汁と膵液が分泌不足を解消するためには?
唾液の分泌量を増やす。
まずは、 「食事の際、よく噛む!」これが一番大事です。のどごしのいい麺類ばかり選んで、「よく噛まず、お腹いっぱいに食べている人」は、逆流性食道炎が回復に向かうということは諦めた方がいいでしょう。噛むという自助努力をせずに、お医者さんや薬に頼ってばかりいては、本末転倒です。
胆のうの機能を高める。
胆汁の分泌不足による胃酸の出過ぎを解消しましょう。
胆汁は、 肝臓で作られます。
肝臓で作られた胆汁をためておけるのが、胆のうです。それだけに、肝臓と胆のうは、セットで疲労しやすいと言われています。胃での消化を終えて、胃の出口:幽門が開いて、食べ物が胃から十二指腸に入ってくると風船のような袋の形をした胆のうは、収縮させて胆管を通り抜けて十二指腸へと流れ出します。
胆のうの機能を高めるためには、肝臓の機能も一緒に高めておく必要があります。
肝臓の機能を高める。
肝臓は、怒りをためやすいと言われています。


ストレスや糖質・脂質のとり過ぎは、肝臓を疲労させます。さらに普段からストレスをためて、怒りをカラダの中にためておくと肝臓の機能低下の原因となってしまいます。後悔・罪悪感を解消しながら、精神的にも肉体的にもバランスを整えておくことが必要なのです。
ストレス、特に怒りの感情は、肝臓に熱がこもってしまいます。この熱した熱が上昇し、食道の粘膜(ねんまく)の水分を蒸発させます。水分が飛ばされることで、粘膜が、粘り気のある痰(たん)となってしまい、食道や気道をふさいでしまします。
食道や気道を痰から守り、通りをよくするために、胃酸を逆流させることは、食道や気道を掃除をするという役目でもあるのです。そのためには、怒りをためないようにしたり、喉の乾燥を予防するということも必要なのです。
肝臓に怒りをためて、肝臓のうっ血が起こると、胆のうにも炎症と腫れ(はれ)た状態が続くと胆のうは、袋の収縮能力を失い、必要なとき、胆汁を出せなくなってしまうのです。

肝臓は、「沈黙の臓器」と言われています。
症状が出たときは手遅れ・・・なんてことのないように、日頃からカラダの変化に敏感になっておきましょう。お酒だけじゃない~肝臓の機能低下をいち早く気づくための23個のサインとは?~
膵臓の機能を高める。
胃酸は、十二指腸へと運ばれると十二指腸も溶かしてしまうほど強力な酸性。
胆汁を出すことで中性にし、十二指腸を守ってくれているのです。胆汁が充分分泌されないと膵臓は膵液を出して中和させようとします。膵液は強力なアルカリ性なのです。



このように、胆のうや肝臓、そして膵臓の機能低下は、胃酸を多く分泌させる原因となっているのです。
糖質と脂質を制限しながら、寝る前の3時間はなるべく食事を空けておくようにしましょう。
まとめ
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
いかがでしたか?
現代医療では胸やけの原因となる胃酸の逆流を悪い症状とばかりみなしています。「逆流を放っておけば、最終的には、がんになってしまいますよ」「長い目で見ながら薬で対処していきましょう」と薬や手術によってなんとかしなければならない状況で悩んでいる人も多いでしょう。
しかし心臓や肺を守るために、胃の入り口を解放し、胃の膨張からも守ろうとしているとしたら?
手術などで胃の入り口を開きにくくする処置をしてしまえば、どうなるか?
冷静に考えれば、自然と分かることでしょう。
副作用のない薬はありません。
極論に聞こえるかもしれませんが、「 逆流性食道炎を放っておくとがんになるのではなく、カラダを守ろうとする症状を薬や手術で止めてしまうことによって、がんになってしまうのではないか?と感じます。
逆流性食道炎も含めて、症状とは、カラダを元に戻そうとする反応であり、治そうとする力なのです。

事の始まりは、肝臓!
- 肝臓の機能が低下すると、胆汁を作り出す機能が低下し、充分な胆汁を作り出せなくなる。
- 脂肪の分解など大切な胆汁が作られないと膵臓(すいぞう)が肩代わりをして、膵液を出し過ぎて疲労する。
- 膵臓の疲労により、膵液が不足すると胃が胃酸を大量に出して、ガスがたまり、胃が拡張してします。
- 胃の中のガスをなんとか外に出そうとし胃の出口が開く。
- 逆流性食道炎。
逆流性食道炎を解消していくためには、肝臓のうっ血・炎症を抑え、肝臓の機能を高めておくことが必須なのです。
肝臓の機能を高め、カラダに必要な分の胆汁を出しやすい環境を作る。
それができれば、膵臓の負担も減らすことができ、右肩のこりも解消されるでしょう。
肝臓・胆のう・膵臓の機能が回復すれば、胃も必要以上に胃酸を出さなくてもすみ、胃がガスで、パンパンに張るといった症状も解消されることでしょう。単に出てきた症状をなんとかしようと対処に振り回されて、大切なものを失わなくてもすむように願いを込めて書かせて頂きました。
逆流性食道炎は、胃が悪いという常識を信じてきたあなたには、「肝臓の疲労が原因」という考えは非常識と思われるかもしれません。しかし、発想を柔軟にすることで、あなたの長引く胸やけや不快な症状の解消にお役に立てたら幸いです。