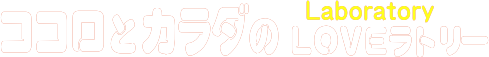血液・血管は、「離れ小島(末端の組織)」に生活物質を運ぶ連絡船のようなもの。血液・血管は、カラダの恒常性を保つための物流部門なのです。
そんな連絡船が嵐でずっと来てくれなかったらどうなると思いますか?


ここで、本題に入る前に、連絡船の主な役割をまとめてみました。

連絡船の主な働きをご覧ください。
- 肺からの酸素を全身に送り、全身からの二酸化炭素を肺に運ぶ。
- 消化管で吸収した栄養を肝臓をはじめとする全身の器官に運ぶ。
- 水分・電解質などを腎臓などの泌尿器系に運んで、体液の濃さを一定に調節する。
- 窒素代謝物や老廃物を泌尿器系に運んで、カラダの外へと排泄する。
- 白血球の食作用や免疫物質(抗体)を作り出す事でカラダを守る。
- ホルモンを全身の狙った器官へと運ぶ。
- カラダの熱を全身に送ったり、皮膚の近くの血管から熱を放出したりして、体温の調節を行っている。


血液の循環が滞っていると様々なカラダの不調に繋がることは、ここで説明するまでもないでしょう。

血液・血管を学ぶにつれ、つい整頓していないと混同してしまうのが、
うっ血と充血。
うっ血と充血(じゅうけつ)の違いが分からないと、お医者さんの説明してくれている内容も分かりにくいもの。
本によって時々、間違った表記もされているので、整頓してみましたので、改めてご覧ください。
うっ血と充血はよく混同される。
うっ血も充血も・・・『カラダ局所の毛細血管網における血液のうっ滞』です。
では、どんな区別があるかというと・・・一般的には・・・
- 静脈の血液が出ていきにくく、うっ滞を起こしているのが、うっ血。
- 流れ込む動脈の血液が増えて、うっ滞を起こしているのが、充血。
と言われています。

充血とは?
動脈からの局所の毛細血管網への血流が増加している状態をいう。動脈性充血とも言われる。充血を起こすと「顔が火照る」または「目の充血」などの表現が示すように、局所は鮮紅色をし、その箇所が熱を持ったり、拍動などが観察される。
うっ血とは?
静脈の還流障害により、局所の毛細血管網の静脈血が増大した状態をいう。動脈性の充血に対して、静脈性充血という事もある。うっ血が起こると局所の青色症(チアノーゼ)や発赤(ホッセキ)、腫脹(ハレ)などが現れ、その状態が続くと浮腫(組織液の異常増加)や出血(血液が血管の外に出る事)などの二次的病変を引き起こす事もある。
引用:『イラスト解剖学』中外医学社
うっ血も充血もなくカラダ全体に、血の巡りをよくしようと思ったら、心臓のポンプ圧だけでは追いつかないのです。



特に ふくらはぎの筋肉は、足先まで行った静脈の血液を重力に逆らって、上に上にと持ち上げてくれる大切な役割をしてくれています。
日段から歩いたり、ケアうすることで、ふくらはぎの筋肉のお手入れをココロがけておきましょう。
横歩きや後ろ歩きを取り入れれば、バランスのいい筋肉の付き方をしますよ。
ウォーキングなどで、前に前にばかり歩いていると、筋肉に偏りが出てしまうので、注意が必要です。
最後に・・・
いかがでしたでしょうか?
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
うっ血と充血の違いが分かるだけでも、お医者さんの説明してくれていることが聞きやすくなるかもしれませんね。
日頃から、ふくらはぎのお手入れをココロがけておくことも大切です。
心臓にばかり連絡船の役割をまかせっきりにしないで、自分で出来ることを一緒に探していきましょう。